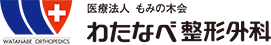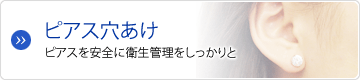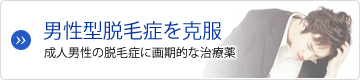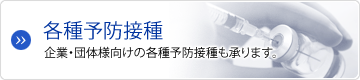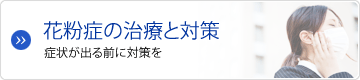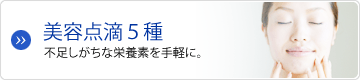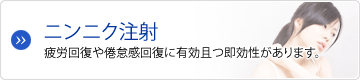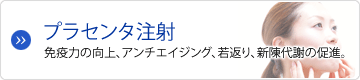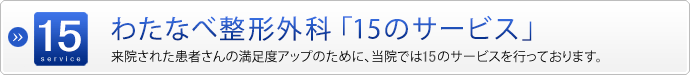自慢話?
先日、成田空港の本屋さんで面白い本を購入しました。家族旅行中、のんびりした時間にでも読もうかと何冊かピックアップした内の一冊ですが、これが久々のヒットでした。
タイトルは「憂鬱でなければ、仕事じゃない」、幻冬舎の見城徹氏とサイバーエージェントの藤田晋氏の共著で、35項目のテーマについて見城氏、藤田氏がそれぞれ2頁ずつ自分の考えを披露し合うというものでした。
これまで私があまり深く考えもせず、自分なりのルールも決めず、何気なくやっていたものにきちっとした意味付けをし、ああ成る程ねと共感できる部分がとても多く、これは見城氏が私と1歳違いということ以上に、これまでの人生を、同じような感性を持って手抜きをせず、真剣に、「瞬間瞬間が人生だ!」という気持ちで歩んで来た者同士の、ある種の親近感を感じさせる内容でした。
帰国後、皆にもこの本を紹介してあげようとネットで何冊か注文した際、そこに掲載されていた70件を上回るカスタマーレビューを読み、ちょっと驚きました。
見城氏の単なる自慢話と切り捨てる書評と、とても刺激的で今後のビジネスや人生に大いに活用したいという好意的な書評、そして中には賛否両論の両書評を論評するものまであり、楽しく読ませてもらいましたが、出来れば自分は、素直にこの本を評価し、さらに自分をレベルアップする糧にしたいと考えています。
何らかの意見や新しい情報に触れた時、それを素直にポジティブに受け止めるか、皮肉っぽくネガティブに受け止めるか、自分の心の持ち様次第かなと思います。
齢を重ねると、ともすれば最初から斜に構えてしまい、様々な場面で知ったかぶりをして、意味もなく批判的な態度を取ってしまったりする方も時々見受けられますが、いくつになってもピュアな心と旺盛な好奇心を失いたくないものです。
ところで、当院待合室「100の引き出しコーナー」には鬼頭隆さんの詩「ステキな人」が 収納されていますが、これは以前リハビリで働いていた、柔道整復師でありカイロプラクターでもあった佐野明文君に紹介してもらったものです。
私はさまざまな場面でこの詩を引用させて頂いておりますが、今でも読み返す度に気持ちを新たにさせられます。
かつては日本もそうでしたが、階層社会の確立した英国では現在でも各階層、各職種内での人々の暮らしがいい意味で確立しており、一人一人が自身の仕事や生活に誇りを持ち、他の階層、他の職種をいたずらに妬んだり僻んだりせず日々の暮らしをエンジョイしていると聞いております。
私も、人の成功や、喜び、楽しみ、自慢話などをおおらかに受け入れ、共感し合えるような心を、これからもずっと持ち続けて行きたいと思っています。