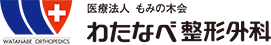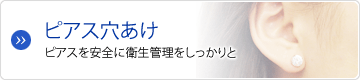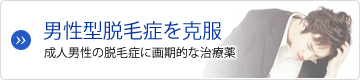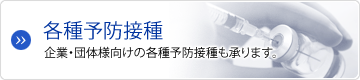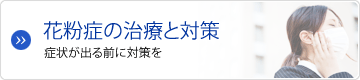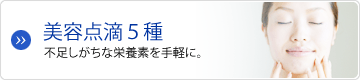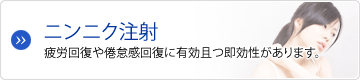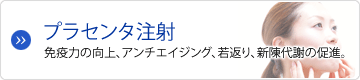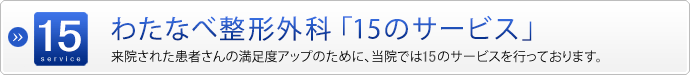Tokyo その住環境としての考察
今から2ヶ月程前、私の従兄が東京で分譲マンションを購入しました。アークヒルズの裏手に位置し、スペイン、スウェーデン、サウジアラビア、アメリカなど、各国大使館が林立する中にそびえ立つ27階建ての立派な建物の15階の部屋でした。大きく開放された窓からの眺望も申し分なく、屋上の共有オープンデッキスペースも快適でした。また建物周辺の環境も素晴らしく、街路樹が整然と植えられ、とりわけ桜のシーズンは最高との事でした。坂を少し下るとお洒落なオープンカフェがあり、木洩れ日を浴びながらお洒落な客達が楽しそうに語らい、食事(グルメな従兄の話では、かなり美味しいとの事)をしており、まるでパリのシャンゼリゼ通りに来たような錯覚に陥りました。
「東京は近い将来大地震に見舞われ、壊滅的なダメージを受ける可能性が高い。」という情報からすると、そこに不動産を購入し住むなど、正気の沙汰とは思えない。この考えの下、少し冷ややかな目で、都内での新築マンション販売の好調さを眺めていた私ですが、今回の体験後多少考え方が変化して来たのを感じています。
私が永遠の命を授かっているのであればいざ知らず、五感が正常で感性が豊かなうちに、自分にとって最も快適と感じられる場所で、自分に残された貴重な時間を刻むことの意味を考えさせられました。
また住む場所を選ぶ際、建物の耐震構造、セキュリティーを含めた管理体制、眺望などはもちろん重要な要素ですが、自分にとってこれらは大体一割程度の意味しか持たず、残り9割を占めるのはそれを取り巻く周辺の環境であると考えています。
さまざまな施設(美術館、コンサートホール、ショッピングセンター、レストラン、etc)へのアクセスの良さ、気持よく散歩やジョギングのできる、治安が良くて緑の多い,瀟洒なプロムナードや、地下鉄などの交通機関が整備されているか、などなど数え上げればキリがありませんが、これらをすべてクリアできる場所があったら是非住んでみたいと考えています。
豊かさ・便利さが東京へ集中することの弊害が叫ばれて久しい中、我々から徴収された税金は首都や県庁所在地に集中的に注ぎ込まれ、多くの地方都市は衰退の一途をたどり、徐々に住みにくく、住んでいても楽しくない街になりつつあります。
天気の良い日曜の朝、朝食のとれる美味しいオープンカフェはなく、夜10時を過ぎると数少ないグルメな店はすべて閉まり、ライブの楽しめるジャズクラブもスタバもない街に私は今住んでいます。自分の納めた税金を少しでも回収する意味も含め、今よりも少しでも快適な居住環境で過ごす時間を増やすということは、考慮に値する案件かなと考え始めました。