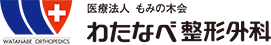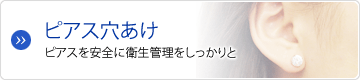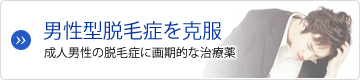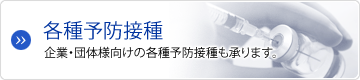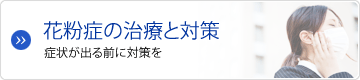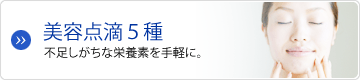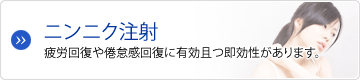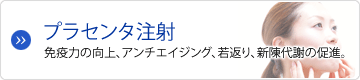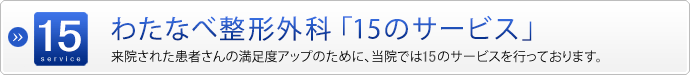日本語の不思議
最近日本語という言語の持つ危うさにしばし考えさせられることがあります。先日亡くなられた野坂昭如氏は、援助交際する少女のことを「個人営業の売春婦」と喝破していましたが、低俗なマスコミ諸氏が本当は由々しき社会問題を、ともすれば美化するような言葉で飾り立て、少女達を安易な売春行為に走らせる昨今の風潮にはかなり違和感を覚えます。
学生時代から相当な悪で、さまざまな人に精神的・肉体的ダメージを与え補導歴もあるような、いわゆる不良でチンピラだった男が、もちろん本人の努力もあったことは認めますが、様々な幸運を得て社会的に成功すると、大半の日本人はこの人物の過去の悪行を「ヤンチャ」という一言で片づけ、まるで免罪符のように許し、むしろ美化するような風潮があることにも違和感を覚えます。社会的に認められ、それなりの評価をされるようになった場合、若い頃悪だった人の方が、真面目に生きて来た人よりも何だか味があってカッコいいと評価する風潮はとりわけ芸能界では顕著な気がします。
いずれにせよ、幼い頃(どう考えても小学生位まで)の罪のないイタズラと中学生以降の他人を傷つける犯罪的な行為はハッキリと区別して、ヤンチャという言葉で一括りにするのはやめて欲しいものです。
さて一般的に外国人にとって日本語は習得するのが難しいという事になっておりますが、私は個人的にはこの意見に懐疑的です。日本語は基本的に母音が多く発音し易く出来ており、またイントネイションやアクセントの位置を決定的に間違えても意味が通じてしまいますが、英語やフランス語ではこうは行きません。要するに日本語というのは単語を羅列するだけで、何とか日常会話レベルは大抵間に合ってしまうのです。
ただし言葉の持つ深い意味や微妙なニュアンスまで正確に伝えたいということになるとその難易度は一気に上がります。一つの単語に様々な意味を持たせたり、同じ事象に対して何通りもの違った表現をすることの出来る日本語は、難しい言語というよりは味わい深く豊かな表現力を持った言語と言えるでしょう。漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字を駆使し、これ程までに完成された奥の深い、絶妙な表現力を持った言語を私は日本語以外知りません。我々日本人は、先人達から継承したこの言語を更に磨き上げ、時代の流れの中で巧みに適合させながら、世界に冠たる言語としての地位を確立し、誇りを持って美しい日本語を流暢に使いこなせるようになりたいものです。
外国人と交流する時は英語、ゆるく心豊かな時間を過ごしたい時は日本語という風に、状況によってさりげなく使い分けることが出来たら素敵だなあと考えています。