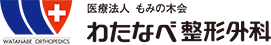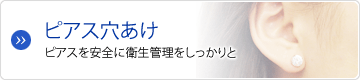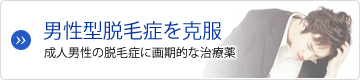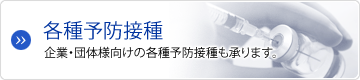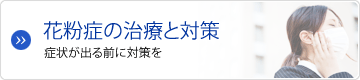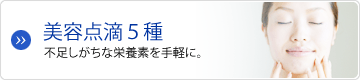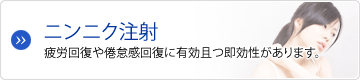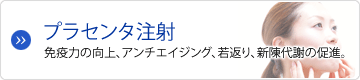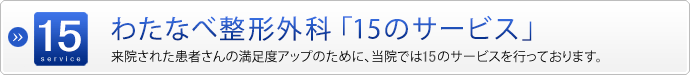国民皆保険の落とし穴
保険証一枚持っていれば、日本中どこの医療機関でも受診できるし、全国均一の料金で保険診療を受けることができます。東大病院の教授が診察しても、卒業したての研修医が診察しても患者さんの払う医療費は同じと言う訳です。しかしここに大きな落とし穴が潜んでいることに気付いていない人が多いようです。それは院内処方・院外処方についての理解が不十分なために起こって来ます。
欧米で主流である医薬分業というシステムは日本ではなかなか普及しませんでしたが、厚生労働省は医療費抑制の切り札として、近年強力な利益誘導政策(院外処方を採用した方が医療機関にとっての経営的なメリットが大きくなる政策)により、その推進に努めて参りました。「医師は薬価差益で利益を上げる為、患者さんを薬漬けにしている。」という厚労省役人の偏見と思い込みに基づき、強引に推し進められてきた「医薬分業」でしたが、残念ながら「医薬分業」となっても医師から処方される薬剤の量はほとんど変わらず、医師達は適正な薬剤を必要な分だけしか処方していなかったことが証明されたこととなり、むしろ調剤薬局の増加によって医療費を逆に増大させるという皮肉な結果となっているようです。
現在の診療報酬体系の中では、全く同じ治療を受け、同じ薬を処方されたとしても、受診した医療機関が院内処方・院外処方どちらを採用しているかによって、患者さんの最終的な支払額は約3割も違って来るということになっています。これは厚労省の指導の下、調剤薬局で実施されている意味不明、有名無実な手数料の加算により支払い額が大きく膨らんでしまう為です。 「わたなべ整形外科H/P (院長からの情報発信箱)」参照
いずれにせよ、保険証一枚持っていれば日本中どこの医療機関を受診しても、全国均一の料金で保険診療を受けることができるという話には、ちょっとした落とし穴が用意されているという事を是非ご理解いただきたいと思います。
現在足利市には、主だった整形外科の施設が7件ありますが、そのうち院内処方を採用しているのは現時点では当院だけとなっています。これは当院の基本姿勢として、常に患者さんサイドに立った、やさしくて分かりやすい医療を提供したいという強い信念の下、病院の利益よりも患者さんのメリットを優先した結果の表れと解釈していただければ幸いです。