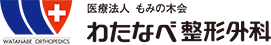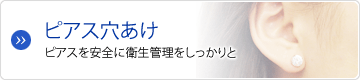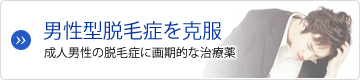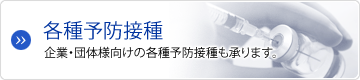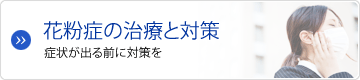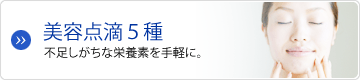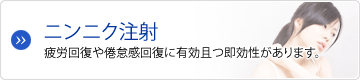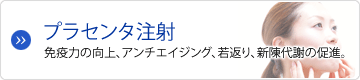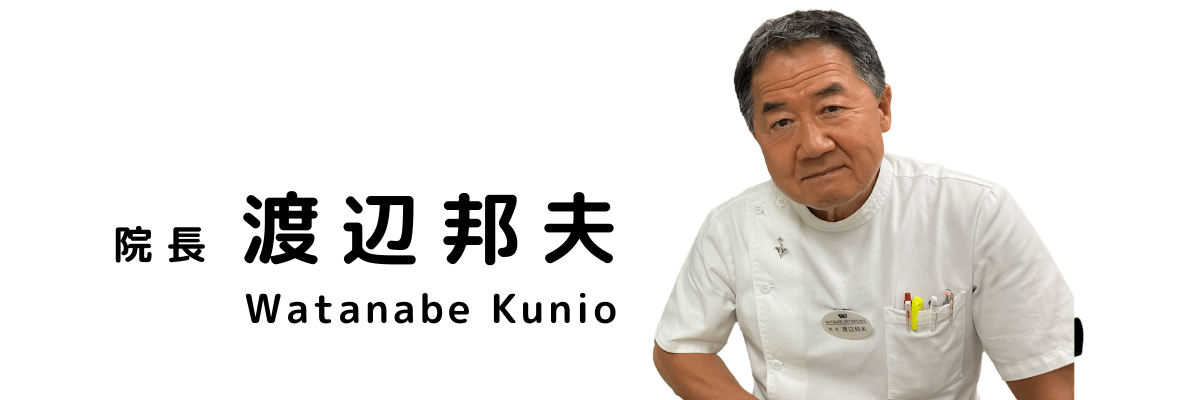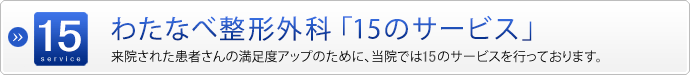日本の食糧問題(特にコメ)
先日農水大臣が意味不明な馬鹿げた発言の末に辞任しましたが、彼は典型的な二世議員でした。後任として登場したのは何と初代から数えて4世代目の世襲議員です。米価の高止まりが彼のパフォーマンスだけで沈静化するとは到底思えませんが、先ずはお手並み拝見といった所でしょうか。さて日本の総人口は2008年をピークとして減り続けており、年間約700万トンのコメ消費量は今後ますます減少することが予想されます。こんな中2024年は例年に比べ101%の豊作だったと言われているにもかかわらず、現在米価が高止まりしている日本の現実は謎でしかありません。そろそろ小手先の応急処置ではなく、JA と農水省そして農水族議員にまでメスを入れる抜本的な改革に着手すべき好機到来かと考えます。まず農水官僚達は思考停止して前例踏襲することを止め、農業に関連した様々な規制を撤廃し、真に農家に寄り添った農業改革を実行し、理屈の通らない補助金の支出で農家のやる気を削ぐような税金の無駄遣いは再検討すべきかと考えます。更に言うなら2018年に廃止したはずなのに未だダラダラと続く減反政策はしっかりと見直し、正確なデータに基づく政策へと変更すること。農業の大規模化、適正化そして最適地での生産に舵を切り、利益追求を可能にすれば、農業はもっと魅力ある職種へと変貌して、やる気のある若者達の参入を促し、国際競争力を持った商品として海外への販路を広げることも可能になると考えます。そしてその成功例は既にヨーロッパ各国に多数存在します。政治家や官僚達は国費観光ではなく本気で視察し、先人達に学んで来て欲しいものです。現在世界先進各国の食料自給率は、カナダ233%、フランス131%、アメリカ121%、ドイツ84%、イギリス70%、イタリア58%、日本38%となっていますが、日本の場合肥料、飼料、種子の大半を海外に依存している為、実際の自給率は10%を切っていると考えるべきであります。ということは、ひとたび世界規模の大きな紛争が起こって物流が滞れば、「世界で最初に飢えるのは日本である」というアメリカの研究者の指摘は、もっと深刻に受け止めて早急な対策を講じるべき喫緊の課題であると考えます。こんな中コメだけは我が国において自給率100%(田植え機の燃料は輸入ですが)と言われています。政治家達は食料安全保障の観点から見ても極めて重要な戦略物資であるコメの問題を1日も早く解決し、国民の不安を払拭してもらいたいものです。