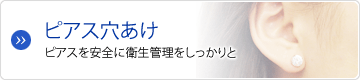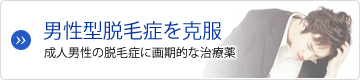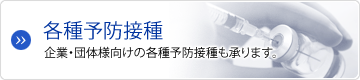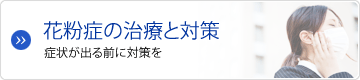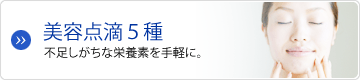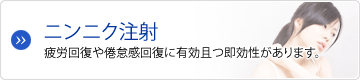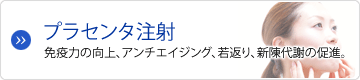日本人の「赤ひげ」信仰について思うこと
先日、1人の有能な経営者として、また人生の先輩として尊敬していた方から、「お前はDoctor Merchantだ!」と言われ、大変ショックを受けました。 せめて「珍しく、経営感覚を兼ね備えた院長」位に言って欲しいものだと、その時は心の中で強く反発しましたが、冷静になって考えてみると、今の40代以上の日本人にとって、理想の医師像とは「赤ひげ」なのかなと、妙に納得してしまい、これは厄介な事だと感じるに至りました。(´・ω・`)
せめて「珍しく、経営感覚を兼ね備えた院長」位に言って欲しいものだと、その時は心の中で強く反発しましたが、冷静になって考えてみると、今の40代以上の日本人にとって、理想の医師像とは「赤ひげ」なのかなと、妙に納得してしまい、これは厄介な事だと感じるに至りました。(´・ω・`)
「赤ひげ」というのは、昭和39年に封切られた 映画監督 黒沢明氏の代表作の一つで、作家 山本周五郎が昭和34年2月、文藝春秋新社より出版した「赤ひげ診療譚」を原作としたものです。「三船敏郎」演ずる赤ひげ先生が院長を務める「小石川養生所」に、不本意な形で赴任した「加山雄三」演ずる青年医師が、最初は反発しながらも、徐々に「赤ひげ」の生き方、考え方に感銘を受け、成長してゆく過程を描いたものです。
「赤ひげ」の、医師としての行動には、私心がなく、ただひたすら患者を治すことのみに思考が集約されています。常に最善の医療を提供することに専念し、自己犠牲と奉仕の精神に充ち溢れた聖人君子として描かれており、山本周五郎が練り上げた架空の人物だからこそ、まさしく人々が求める理想の医師像となっていると感じました。たしかにこういう架空の人物である「赤ひげ」と対比して、現代の医師を批判することは、実に溜飲の下がる事かも知れませんが、果たして現在の医療制度の枠組みの中で、「赤ひげ」のような人間が存在しえるのか、皆さんで考えていただきたいと思います。
我が国では、1948年頃から健康保険が普及し始め、昭和36年(1961年)に世界に冠たる国民皆保険が成立し、国民を取り巻く医療環境は劇的に改善しました。しかし1950年頃から、医療費が年々増加することを極度に恐れる厚生官僚たちにより、保険医療を担う医師たちは、医療費の請求をめぐって、指導や監査、審査によって診療の内容にまでさまざまな制約や圧力を受け始めることになりました。そして1952年10月頃から、厚生省の監査を受けた直後に自殺する保険医が後を絶たず、頭ごなしに怒鳴りつけ、反論を許さない、高圧的で脅迫めいた言葉を多用する指導技官たちの言動が、医師の人格を無視した人権侵害だとして国会でも問題になり、厚生省が追及されるという事態にまで至りましたが、なんら改善もなく経過しておりました。しかし1993年10月11日、地域医療に情熱を燃やす青年医師が、厚生技官による個別指導後自殺したことがきっかけとなり、マスコミを巻き込んだ社会問題へと発展する事になりました。
「開業医はなぜ自殺したのか」矢吹紀人著(あけび書房)
この事件後も多少改善されたとはいえ、基本的には指導や監査の強化を通じて、医療費を削減する事を目的とする政策が現在も行なわれているのが日本の医療の厳しい現実です。
現在でも厚労省は一貫して医療費抑制策を採り続けており、医療機関の経営状況は年々悪化しているというのが現状ですが、何の企業努力もせず、厚労省の指導通り漫然と診療を続けているとどうなるか、全国の国公立病院の8割が赤字という数字が示す通り、多くの医療機関が破たんします。アメリカのおよそ半分の医療費で、世界最高水準の日本の医療が維持されているのは何故か? それは医療関係者の自己犠牲ともいえる、ひたむきな努力がこれを支えているからに他なりません。
「日本の医療に未来はあるか」鈴木厚著(ちくま新書)参照
今の時代「赤ひげ」のような医師が診療所を開設すれば、まず間違いなく一年以内に倒産します。経営感覚の乏しい人間が組織を率いることになると、現在の診療報酬のシステムの中では、まず間違いなく大赤字です。
常に患者目線で、患者さんにとって最高の医療を展開する事を目指し、しかも窓口での患者さんの負担を極力抑えながら、職員の待遇も高く維持する為に、院長には、ある時は医師として、そしてある時は経営者としての、二つの顔を持つことが求められていると認識しており、この姿勢を「Doctor Merchant」としてしか見ることができないのは、かなりさみしい話かなと思います。